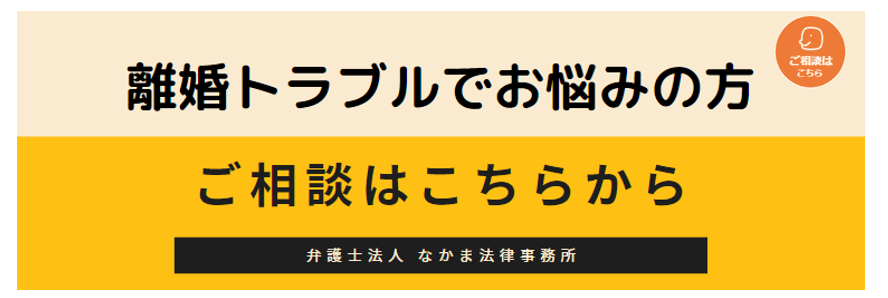養育費の不払い分を強制執行で回収するには?
- 養育費
養育費を支払ってもらえないケースは、現実にはまだまだたくさんあるのが実情です。もっとも、法律には、養育費を回収するための仕組みがきちんと存在します。そのため、この仕組みを活用することで、支払ってもらえるようになり得るケースもたくさんあります。
本記事では、養育費を支払ってもらえずお悩みの皆様へ向けて、養育費を回収するための法律の仕組みである、強制執行についてご説明いたします。
養育費における強制執行とは
養育費とは何か
養育費とは、離婚後に未成熟の子の親権者ではなくなった親から、親権者である親に対して支払われる、未成熟の子の生活費です。あらかじめ「月額〇万円を子供が20歳になるまで支払う」というように約束したうえで、そのとおりの額を実際に毎月振り込んでいく、という形が基本となりますが、ケースによっては、大学・私立学校の学費や、病気・事故等による突発的な医療費といった、「特別の費用」と呼ばれる費用の支払いのあり方についても取り決めることがあります。
いずれにせよ、約束したとおりの額を、任意で支払っていくというのが原則となります。したがって、毎月きちんと支払っているのに後述の強制執行の手続をすることはできませんし、支払いが遅れたり支払いがなかったりという状況があるならば、まずは任意できちんと支払ってくれるよう要請するという手順を踏む方が良いと考えられています。
強制執行とは何か
強制執行とは、法的に認められた権利(≒債権)と義務(≒債務)があるにもかかわらず、義務者側がその義務をきちんと果たさない場合に、強制的にその義務を果たさせるという手続です。養育費の場合でも同様で、前述のとおりまずは義務をきちんと果たさない状況、すなわち養育費をきちんと支払わない状況が存在する必要があります。
強制執行をするための条件
執行力のある債務名義の正本を取得する
「執行力のある債務名義の正本」(民事執行法22条)とは、強制執行ができる理由、すなわち、養育費の支払いを受けられる権利があることを示す文書のことで、具体的には、調停調書、審判書、強制執行認諾文言付公正証書が該当します。
大前提として、強制執行のためにはこの債務名義がないといけないため、もし所持していない場合は、まずは債務名義を得るための手続き、例えば養育費請求調停を申立てる等する必要があります。
債務名義について、送達証明書を取得する
上記の債務名義が、きちんと債務者に届けられている(専門用語で「送達」といいます)ことも強制執行の条件となるため、その証明書である送達証明書も取得する必要があります。これは通常、その債務名義を作成した機関(裁判所や公証役場等)に連絡して取り寄せる必要があります。
相手方の現住所を把握する
強制執行を申立てる場合、その申立て先の裁判所は債務者(=養育費を支払わない相手方)の住所地を管轄する裁判所であると決められています。また、強制執行は本来自由に処分できるはずの財産を強制的に出させる強力な手続きであるため、手違いで無関係の他人を巻き込んでしまうと大変です。そのため、養育費を支払わない人本人であることをしっかり特定して示す必要があり、それ故に申立書に債務者の住所を記載することが求められます。
したがって、相手方の現住所がどこかということを把握することはマストとなります。
強制執行で差し押さえることが可能な財産
一般的に、強制執行で差し押さえることが可能な財産としては、債権(相手方が第三者に対して有している金銭の支払いを受けられる等の権利のこと)、不動産、動産があります。
このうち、支払ってもらえない養育費を強制的に支払わせるという場面では、給与債権、すなわち相手方が自身の勤務先に対して有する給与債権(給与としてお金を支払ってもらえる権利)が選択されることが通常です。したがって、以下の「強制執行の手続きの流れ」では、給与債権を差し押さえ対象とする場合の流れについてご説明します。
強制執行の手続きの流れ
①債権差押命令申立書一式を裁判所に提出する
基本的に申立てに必要となるのは、債権差押命令申立書の本体、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録の4つの書類です。これらを作成し、債務名義の正本、送達証明書、相手方の勤務先の登記簿謄本(登記事項証明書)等を添えて、裁判所に提出します。なお、ケースによっては、住民票等ここに挙げた以外の資料の提出も必要となる場合があります。もし提出した書類に不備や不足がある場合は、裁判所から連絡してもらえますので、裁判所の指示に従って追完するようにしましょう。
②裁判所から債権差押命令が発令される
必要書類を全て提出し、問題がなければ、裁判所は債権差押命令を発令します。その後、裁判所は、債務者と債務者の勤務先(専門用語で「第三債務者」といいます。)に債権差押命令の正本を送達します。
③第三債務者から取立てをする
債権差押命令の債務者・第三債務者への送達が終わった後、債権差押命令を申立てた人には裁判所から送達通知書が送付されます。この書類に記載されている債務者への送達日の翌日から1週間が経てば、第三債務者から直接給与のうち差押えた分の支払いを受けられるようになりますので、第三債務者に連絡をして、支払いをしてもらいます(専門用語で「取立て」といいます。)。
④裁判所へ取立届を提出する
第三債務者から支払いをしてもらったら、その旨を記載した取立届を忘れずに裁判所へ提出します。
養育費の回収でお悩みの方は弁護士法人なかま法律事務所へ
以上、本記事では養育費を回収するための強制執行の仕組みについて解説しました。弊所では、養育費回収の経験豊富な弁護士とスタッフが、あなたのお悩みに寄り添い、解決のために全力でサポートをさせていただきます。平日18時までの初回相談は無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当事務所の養育費回収代行サービス
当事務所ではシングルマザーに向けの養育費回収代行サービスを行っております。養育費におけるトラブルとして、以下のようなご相談をよく承っていました。
「調停で合意していたり、公正証書を作ったにもかかわらず、養育費が支払われていない」
「収入が減ったから払わないと言われてしまった」
「離婚時に養育費の約束をできなかったが、やっぱり支払ってほしいと考えている」
このようなご希望に添えるために、弊所では「着手金ゼロ」、「自宅からのZoom相談可」、「初回無料相談」にて対応をさせていただくことと致しました。詳細はこちらからご覧ください。